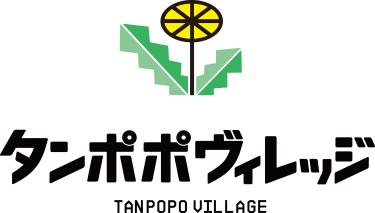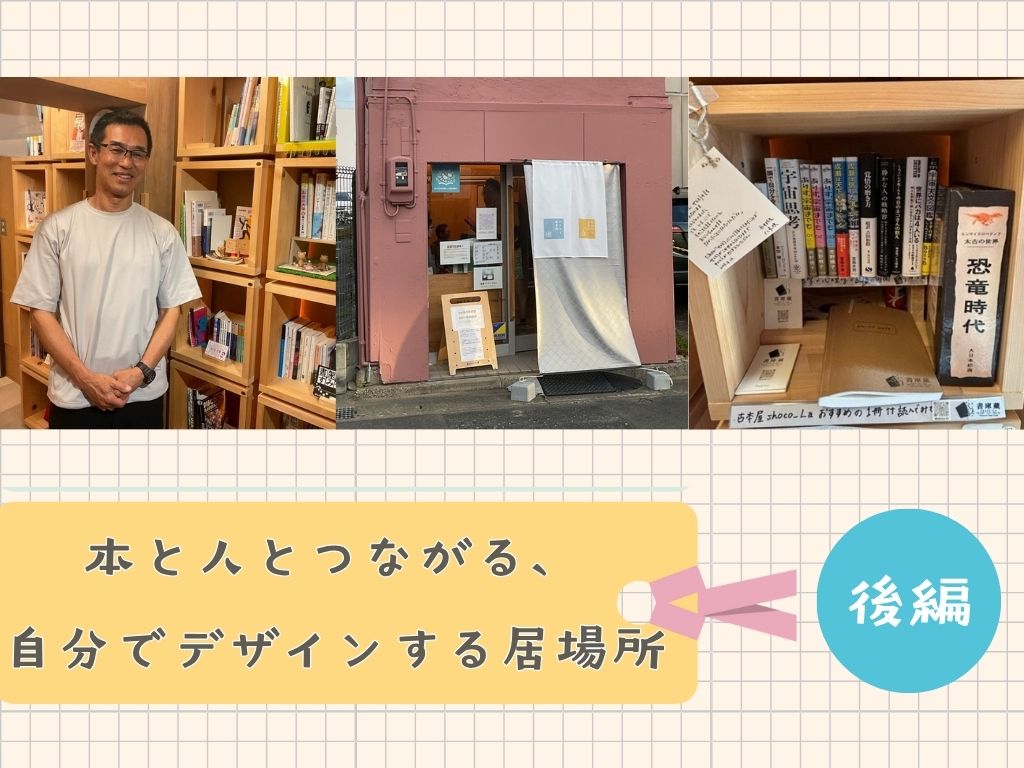苔テラリウムを通してみつめる自分の内面
「SNS映え」という言葉がトレンドになっている今、オデカケ先を選ぶときは、美味しそうな料理や珍しい体験を写真・動画で撮影しSNSに投稿できるかどうかを基準にする人も多いのではないでしょうか?
写真や動画を「自己表現」としてSNSに投稿することが流行ですよね。
しかしながら、オデカケ先で食べられる料理、観光場所は「みんなが撮れる」もの。
その場所に行けば誰でも同じ経験が出来るものも多いです。
「自分の外側」にある経験ではなく、「自分の内面」を表現するSNS映え。
せっかくオデカケするなら、あなたにしかできない、ただ一つのSNS映えを手にしてみませんか。
今回は『苔テラリウムワークショップ』をご紹介します。
苔テラリウムってどんな趣味?
テラリウムの語源は、ラテン語です。「テラ(terra)= 大地・陸地」と「リウム(arium)= 場所」を合わせた造語であり、ガラスなど光が通る密閉された透明なケースの中で、陸上の生き物を育てる方法のことを言います。(道草 ホームページより引用 https://www.y-michikusa.com/blog/blog/1033/)
苔テラリウムではガラスの器の中に、石や木を置き、植物の「コケ」を育てます。
「コケ」が植物であるため製作して終わりではなく、部屋に置けば「変化するインテリア」として楽しむことができますよ。
器の中という限られた空間にコケという生き物が育つ自然を創造することは、自己表現の1つでしょう。ひとつとして同じ環境はなく、石や木とコケを配置する中で自分の考え方や理想が見えてくることが魅力です。
自分にしか作れない、「変化する」作品を通して、自分の内面と向き合える趣味だと言えますね。
今回の訪問先!東三河唯一の苔盆景専門店「mossloulan楼蘭」

JR豊川駅からクルマでおよそ20分。
今回お邪魔したのは東三河地区で唯一の苔盆景専門店「mossloulan楼蘭」さん。
店内には、店主の松井さんが製作・販売している苔盆景や苔テラリウムの作品がズラリ。草木と苔と器の調和がとれていて美しいです。

苔テラリウムワークショップを体験!
入店してまもなく、「まずはワークショップで体験してみましょう!」
店主の松井さんからワークショップの打診をいただきました。体験することで感想やもっと知りたいことが浮かぶから、とのことで。
まずは器選びから。ガラス製の器には大きく分けて2種類あり、横方向に広がりがあるものと、高さ方向に広がりがあるものです。
今回は2人で参加し、器は1種類ずつ選び製作しました。
苔テラリウムでは器の中に、土や砂、苔を配置して自分の世界を表現していきます。
一般的に土や砂を最初に入れるのですが、松井さんが最初に入れたのは「水苔」。
水苔を敷くのは松井さん独自の製法とのこと。そのわけは器の中を保湿して手入れをしやすくするためなんだそうです。

この製法でつくった苔テラリウムでは、底面に敷かれた水苔が命を吹き返して地表面に出てくると教えてくださいました。「出てくる姿がとても可愛いですよ。」と松井さん。

水苔はレイアウトの土台になるため、遠近法を用い、手前は低く奥は高くなるようにスプーンで押しつぶします。乾燥状態でも、スプーンで押しつぶされても、水をあげれば土を押し上げてこれる水苔。生命力の強さに驚きました。


水苔を敷き詰めた後は、赤玉土などをブレンドしたオリジナル土を水苔が見えなくなるくらいに広げていきます。粘り気のある土は崖のようにそそり立つ水苔の壁にもくっつきます。

レイアウトを引き立たせるのが小石の素材。
これは松井さんが河原で拾ってきたもので、色味や形に個性があります。石の欠けている面を指さして、「1つ1つの石には『欠点』のような面があります。」と説明する松井さん。

“欠点”というと短所だったり、マイナスな面に思えたりしますが、松井さんの言う『欠点』は違いました。
「欠点は自然界では魅力です。前面に出してあげることで輝くんです。」

1つの石でも360°回して見ると、つるっとした面やデコボコな面を見ることができます。
松井さんの言う『欠点』とはデコボコした面のことで、表面の凹凸に影がつき、器の中の空間に奥行きを感じさせます。その石にとってどの面が輝けるかを探る作業です。まるで石との対話。

レイアウトのコツは、実際の山や滝、川のせせらぎをイメージすること。器の限られた空間に自分の理想郷ともいえる環境を構築します。
水苔でつくった高低差を活かして石を配置することで、滝の壁面や山の斜面を縫うようにして流れる川を表現できます。

滝や川の水は砂によって表現。白や青、緑の砂には役割があり、例えば白色の砂は夏の山を想像した時には「小川のせせらぎ」を表し、冬の山を想像すれば「降り積もった雪」に見えてきます。
見る人によって想像される世界が変わる。それもまた、苔テラリウムの魅力の一つです。

いよいよ苔を貼る作業へ。使用する苔は「ホソバオキナゴケ」や「ヒノキゴケ」、「コツボゴケ」など5種類ほど。一口に「コケ」と言ってもその姿は別物で、緑の絨毯のような苔や、上に伸びた背の高い苔まで様々です。
苔には根っこがなく、成長と共に少しずつ横に広がっていきます。塊をばらしたり、茶色く変色した部分はちぎったりして土に植えていきます。

背の高い苔は頭を揃え、好みの高さで植えるために下の部分を切り取ります。


「ピンセットはもっと立ててください。」
「コケの下の方をもう片方の手で押さえて、ピンセットだけゆっくり抜きます。」
「もっと奥まで差し込みます。まだ植わってないです!お手本見せますね。」
ワークショップの最中、松井さんから熱のこもったアドバイスを受けることも。
松井さんが好きな「苔」を使って、よりよい作品を作ってほしい。
そんな想いが、ハキハキとした声と口調から伝わっていきます。

ワークショップでつくった苔テラリウムが完成!
製作に要した時間は1時間ほど。夢中になって製作した時間は、あっ!という間でした。
完成した作品を店内の撮影ブースに置いてパシャリ。2人でワークショップを体験し、選んだ器も世界観も異なる作品ができました。


苔テラリウムワークショップを終えて

苔テラリウムワークショップを体験してみて、自分がイメージした自然を小さな器の中で再現できた達成感を感じることができました。
製作は選択の連続です。石が魅力的に映る角度をさがし、配置していく作業は自分の内面を見ているようで、製作を終えた時には、なにか「すがすがしい」気持ちに。
つくった苔テラリウムは自宅に持ち帰ってからも、苔の変化を楽しめることが魅力です。
日々のお手入れは苔の表面が乾いたら霧吹きで水をあげること。自宅での管理方法も教えてくださいました。美しい新芽が出てくる様子を見れたときには、とてもが癒されますよ。
自己表現の手段がSNSに傾いている今、mossloulanの苔テラリウムワークショップに参加して小さな器の中にあなたの内面を投影してみませんか?
mossloulan楼蘭 松井さんに聞く「苔の魅力」 インタビュー編はこちら ↓
SHOP INFOMATION
| 店名 | mossloulan楼蘭 |
| 住所 | 〒441-0105 愛知県豊川市伊奈町南山新田158番2 |
| 電話番号 | 0533-78-3879 |
| https://www.instagram.com/mossloulan/ | |
| 営業時間 | 9時〜17時 |
| 休業日 | 火曜日 |