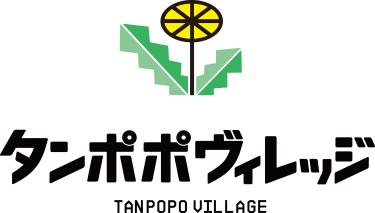筆との出会いを導く挫折と決断~中西由季さん~
子供のころの夢、覚えていますか?
今回は豊橋の伝統工芸品である「豊橋筆」の職人、「中西由季」さんのお話です。
「女性だから。」「地元じゃないから。」という門前払いを受けてなお、折れずに進んだ「職人」という道。
そこにあったのは子供のころからの「職人ってかっこいい」という熱い憧れでした。
ものづくりに人生を注ぎ込んだ彼女の半生とは—。

豊橋が誇る伝統工芸品
そもそもなんですが、【豊橋筆】というのは知っていますか?
普段皆さんが何気なく過ごしているであろう豊橋の伝統工芸品である「豊橋筆」。
実は日本の筆の中では広島県の「熊野筆」に次ぐ第2位の流通量を誇っており、高級筆としての全国シェアは70%にも上ります。
豊橋筆の特徴は水を用いて毛の選別をする「練り混ぜ」という技法を用いるところにあります。
一般的な筆は乾いた状態で加工する一方、豊橋筆は先が切れている毛を一本一本丁寧に取り除いているため筆先が割れにくいそうです。
そんな豊橋筆を作る中西さん。 彼女の「ものづくり」のルーツは実は小学生にまでさかのぼるようで……

実際の練り混ぜ工程
ものづくりが好きだった少女時代
幼いころから手芸が好きだった中西さん。
小学生の頃に一番好きだった科目はもちろん図工だったそうで。
「ずっと図工の時間が続いてくれれば……。」
とあの頃の気持ちをつぶやいていていました。
落ち着きがなく興味のあるものにしか集中できないという性格で、じっと座っていることができなかったという中西さん。
勉強をするのは苦手だった一方で、物を作ることや絵を描くことには深く熱中していたそう。そんな性格が中西さんを、さらにものづくりの世界へ誘ったのでしょう。
「ものづくりを仕事にしたい。」
中西さんはこのころから、そう熱く夢を持っていました。
職人さんってかっこいい
もとよりものづくりの世界に魅了されていた中西さんですが、高校に入るとささやかな出来事から職人にあこがれを持ちます。
高校へは自転車通学をしていた中西さん。
ある日の登下校時に自転車が不具合を起こし、走りはするものの走行中に進みづらいと感じます。
故障した自転車で毎日使うのは大変だということで自転車屋さんに持ち込んで修理してもらうことに。
自転車屋さんはその自転車を見ると、職人のような手さばきで少し手を加えすぐに直してしまいました。
その修理後の自転車に乗ると、なんと見違えるほど乗り心地が良いのです。
高校生の中西さんは感動して、
「職人さんってかっこいい、私もそうなりたい。」
と思ったそうで、幼いころからのものづくりを仕事にしたいという気持ちがより一層高まることになったそうです。
道具をいいものにするっていいな。
学生時代に勉強はあまり得意でなかったという中西さん。
学校の先生に勉強が好きになるにはどうしたら良いかと相談すると、こんなアドバイスが帰ってきました。
「いい道具を使えばやる気が出るよ。」
実際に100円の消しゴムを1,000円の物にした先生は、消しゴムを使うことが楽しみになり自然とモチベーションが上がったそう。
先生の意見を取り入れシャーペンを高級品にしたところ、中西さんもそのシャーペンを使い文字を書くのが楽しみに。
その影響で、勉強が今まで以上に楽しく感じたとのこと。
このことから道具の持つモチベーションを引き出す力を実感したそうです。
「道具を良いモノにするっていいな。」
中西さんは“道具”を作るという立場だけでなく使うという立場でも好きになっていきました。
そして、ものづくりに対してはこんな思いも持っていました。
手芸が楽しくつい熱中しすぎては、気付けばたくさん作りすぎてしまうこともあった中西さん。しかし、どれだけ作っても、使ってもらわなければ道具としての価値は生まれません。
中西さんは「作ったからには、誰かに使ってもらいたい」と感じるように。
デザインがどうこうよりも、誰かが使ってくれるものを作りたい—そう思うようになったのです。
伝統って何だろう
高校を卒業した中西さんは、京都にある伝統工芸大学校の金属学科に進学しました。
ものづくりを学ぶ環境ということもあり、周囲には同じく手を動かすことが好きな仲間が多く、今でも交流が続く伝統工芸士の友人もいるといいます。
充実した大学生活を送っていた中西さんですが、大学2年生になり、少しずつ将来の進路を意識し始めた頃、ある疑問が頭をよぎります。
「伝統って、何だろう?」
その答えを求めて考えを深めるうちに、中西さんの関心は海外へと向かい、タイの山岳民族が守る自給自足の暮らしに強く惹かれるようになります。
そして春休みを利用し、タイの「アカ族」という集団の村で15日間のボランティア活動に参加しました。
日本とはまるで違う、自然と共にある生活の中でホームステイを体験し、現地の文化に深く触れる時間となりました。
滞在中、中西さんは次第に、近代化の波によって伝統文化が失われつつある現状を肌で感じたそうです。
しかし同時に、「伝統とは、身の回りにあるものをいかに最高のものにするか」という気づきも得ることができました。
この経験が、後の中西さんのものづくり観に大きな影響を与えていきます。
刃物職人への志
日本に帰ってきた中西さんは、自分がなんの伝統工芸士になればよいかを考えるために日本中の様々な伝統文化を見て回ります。
その過程で、「せっかくなら、学校で学んできた金属の技術を活かしたい」と考えるようになりました。
しかし、金属を用いた伝統工芸品の多くは装飾品であり、中西さんが理想とする「使いやすい道具としてのものづくり」とは、方向性が異なっていました。
(金属であり、なおかつ普段使いの伝統工芸品)という彼女の求めている条件に合致する工芸品はとても少なく、唯一「刃物」だけが彼女のしたかったものづくりに合致していました。
「デザインよりも技術を求めたい。」
そんな想いのもと中西さんは刃物職人の道を追い求めることに。
卒業して就職となった時には、中西さんは土佐や新潟、堺などの刃物職人に弟子入りを求めます。
挫折
刃物職人を志ざしていた中西さんは、全国各地のあらゆる職人に弟子にとってもらえるよう懇願して回ります。
しかし、職人たちからの返答は残酷なものばかりでした。
「職人は時間が必要。女性は出産や子育てがありその後に戻ってくる保証がない」
「地元であれば弟子としてとってあげたかも」
地元の人間ではないうえ、女性の中でも小柄な体格だった中西さん。
刃物の職人は男性社会だったこともあり、ことごとく弟子入りを断れてしまいました。
結局弟子入りを受け入れてくれる職人は居らず、中西さんは刃物の道をあきらめ生まれ故郷である豊橋に戻ることに。
帰ってくるときの心境を伺うと、少し寂しそうな表情で
「その時はね。『出戻りかよ』って、思いましたよ。」
とぽつり
その一言には、大きな挫折を経験した中西さんの心の内がにじんでいるようでした。
決断。そして豊橋筆職人へ
豊橋に帰った中西さんは、再び就職活動のスタートラインに立つことになります。
就職先を考える中で、「ものづくりを第一にしたい」という思いから、工場のライン作業なども選択肢に浮かびましたが、それを選ぶことはしませんでした。
やはり、幼いころから抱いてきた“ものづくりへの情熱”や「ひとりで作り上げたい」という想いは消えておらず、中西さんは職人として生きていく道を諦めることはできなかったのです。
刃物職人を目指していたときに、「地元なら弟子に取ったかもしれない」と言われたことを思い出し、「地元なら……」という一縷の望みに賭けて、改めて地元・豊橋について調べてみました。
その中で、豊橋には「豊橋筆」という伝統工芸があることを知ります。大学入学前は「そんなのがあるんだ」程度の認識だったそうですが、卒業後の中西さんにとっては「見た目」ではなく「使う」を重視した伝統工芸である豊橋筆は求めていたものでした。
中西さんは豊橋筆の職人を訪ね歩き、弟子入りを志願しました。
しかし、たとえ地元であっても「女性だから」と断られることも多く、厳しい道のりが続きます。
そんな中、川合福男さんという方に弟子入りをお願いします。
いつものごとく弟子入りを断られてはいたものの、川合さんの断り方が弱いと気づき「押せばいけるかも?」と感じたそう。
中西さんは川合さんに押すに押す形で最終的には「目が真剣だったから。」という理由で弟子入りを認めてもらうことに成功しました。
豊橋筆の技術を教えてくれる師匠ができたことによって、中西さんは晴れて豊橋筆職人としての道を歩み始めたのです。
実際に筆づくりに取り組むうちに、中西さんは
「動物の毛が、“筆”という道具へと形を変えていく過程がかっこいい」
と感じるようになりました。
さらに、子どもから大人まで幅広く使われる筆という存在が、自分の「使いやすい道具を作りたい」という想いにも通じており、
「やっぱり私には“筆”だ!」
と確信を深めていきました。
これまでで一番苦労したことは?と尋ねると、しばらく考え込んだあとに、
「長時間あぐらをかいて作業するのがつらいことですかね」
とぽつり。
すぐに辛かったことが出てくる人も多い中で思い返すのに時間がかかるほど、これまでの歩みを前向きに楽しみながら過ごしてきたのだと感じました。
師匠と弟子の関係
師匠に当時のことを聞いてみると、「実は、何度か断ったつもりだったんだけどね」と笑って答えたそう。
けれど、中西さんが諦めずに熱意を伝え続けたことで、押しに負ける形で弟子入りが叶いました。
「師匠と弟子」と聞くと、怒られたり、厳しい指導を受けるような怖いイメージを持つ人も多いかもしれません。
しかし中西さん自身は「怒られたことって、実はあまりないんです」と話します。
その裏では言葉にしない気遣いを見せてくれることもあったそうで、作っていた筆が売り物にならない時は、目の前で直接指導するわけではなく陰に隠れて捨てていたそうです。
静かな優しさがにじむ、そんな師弟関係が続いています。
師匠の川合さんも書道をたしなんでおり、筆職人ということもあって筆には不自由しません。
そのためか、使った筆をあまり洗わないのが玉にキズ。
中西さんが師匠の家を訪ねると、
「師匠、また洗ってないじゃないですか〜」
と、笑いながらツッコミを入れるのが恒例になっているのだとか。
ほっこりするエピソードからも、ふたりの温かな関係性が感じられます。
弟子入りから10年。そろそろ自分の工房を構えてもいい頃だろうと、中西さんは独立をすることに。
とはいえ、今でも師匠や他の職人たちとの交流は続いているそうです。
筆作りで最も難しいのは、筆の良し悪しが数値で出ないために「この筆がいい。」と自分で判断することができないことだそう。
今でも最終確認は師匠にお願いしているといいます。
また、中西さんは多くの書家さんと直接やり取りしており、その声に耳を傾けながら筆づくりに取り組んでいます。
「書家さんってお堅いイメージがあるかもしれませんが、実はすごく元気でパワフルな方が多いんです」
と笑顔で話す中西さん。
「この筆とても良いよ。これをこうしたらもっと良くなるね。」
という使い手の要望に寄り添う
彼らの要望に応えたいという思いが、彼女の仕事のモチベーションとなっているようです。
中西さんの現在行っている活動。
中西さんは、筆職人として技術の探求を欠かしません。
豊橋筆の伝統が50年後、100年後と続いていくためには、時代ごとに変わる流行への対応も必要です。
例えば、細筆には本来イタチの毛が使われますが、近年その価格が高騰しています。
そこで中西さんは、「良質な細筆はイタチの毛でしか作れない」という固定概念を覆し、他の動物の毛でも同じ書き心地の筆を作れるよう日々研究を重ねています。
また中西さんは、今や職人として筆をつくるだけでなく、さまざまな活動を通じて「職人の世界」を社会に広めようと挑戦を続けています。
例えば、豊橋市内の小学生を対象に筆の仕上げ体験を行ったり、端材を使ったコンテストを企画したりしています。
これらの取り組みには、「豊橋筆を知ってもらいたい」という想いだけでなく、「職人=怖い・厳しい」という偏見をなくしたいという願いも込められているそうです。
さらに「職人の姿をもっと身近に感じてもらいたい」と、SNSを活用して日々の制作風景や筆づくりの面白さを発信するなど、情報発信にも力を入れています。
展示会では、自らの髪の毛を使って筆をつくるという驚きの作品を展示したこともあるそうです。
その異様な作品に対して「少し怖い」という声もあったそうですが、中西さん自身は「すごく面白い試みだった」と振り返ります。

中西さんはこう語ります。
「自分がものづくりを楽しんでいることを、もっと多くの人に知ってもらいたい」
今の子どもたちは、どちらかというと現場での仕事よりデスクワークに憧れる傾向があるそうです。
そんな中で中西さんは、現場で手を動かして何かをつくる楽しさや誇り、そしてその奥深さを、未来の世代にしっかり伝えていきたいと考えているとのこと。
最近では、猟師さんとのご縁から、捕れた鹿の毛を使った筆づくり体験や、鹿肉の焼肉を楽しめる“フェス”のようなイベントも企画しているそうです。
ものづくりの面白さを五感で伝える取り組みを、さらに広げていこうとしています。
まだ企画段階とのことですが、実施されたらぜひ参加してみたいですね。
そして現在、中西さんには三つの目標があります。
1つ目は、生まれ育った地元に「職人」としての技術を認められること。
2つ目は、後継者を育て、養っていける体制や資金を整えること。
そして3つ目は、書くだけではなくさまざまな用途で使える筆を作ること。
「筆をつくる」ことを通じて、文化と人をつなぎ、未来へと紡いでいく――。
中西さんの挑戦は、これからも続いていきます。
SHOP INFOMATION
| 店名 | 筆工房由紀 |
| ホームページ | トップページ – 豊橋筆 筆工房由季 公式サイト |
| 住所 | 〒441-8157 愛知県豊橋市上野町字新上野11-2 |
| 電話番号 | 090-9337-0290 |
工房に来られる方は事前にご連絡ください。